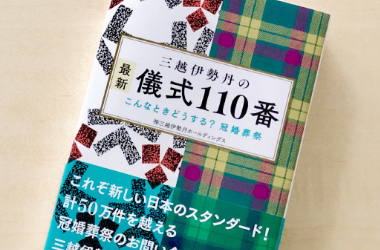仏式

通夜
現代では、「半通夜」といって午後6~7時頃から始まり、午後9時頃に終わるのが一般的です。その後、残ったご遺体や近親者が、ロウソクや線香を絶やさずに一晩中交代でご遺体を守ることがあります。
喪家(死者を出した家族)は、弔問に対するお礼とお清め、故人の供養の意味を込めて、酒、ジュース、寿司、つまみなどの軽い食事をふるまいます(通夜ぶるまい)。弔問された方は、とくに用事がなければ、通夜ぶるまいを受けるようにします。
※1 お逮夜(たいや) (ご逝去の日を入れて6日目)
忌日法要の前日を「お逮夜」といい、この夜に読経して「逮夜法要」を行う習慣が、関西などにはあります。
※2 初七日忌
近親者と親しい人たちでのご供養。後飾りは、より簡略にします。
※3 忌明け法要(七七日忌) 五七日忌ですることもあります。
忌明けには、近親者のほか故人と親しかった人を招き、法要を営んだのち、おもてなしをするのが一般的です。
ご返礼品をお届けする場合は、この日以降に行います。
百か日忌
近親者で供養するのが一般的です。
神式
十日祭(亡くなられた日から十日目)
仏式の初七日忌にあたり、身内と親しい方で霊祭を行います。
二十日祭(亡くなられた日から二十日目)
三十日祭(亡くなられた日から三十日目)
四十日祭(亡くなられた日から四十日目)
一般には遺族だけで霊祭を行います。
五十日祭(亡くなられた日から五十日目)
仏式の七七日忌にあたり、忌明けとなります。親しい方を招いて霊祭を行い、おもてなしをするのは仏式と同様です。ご返礼品をお届けする場合は、この日以降に行います。
キリスト教式
三日目・七日目
カトリックでは追悼ミサ、プロテスタントでは記念式を行います。
三十日目の追悼ミサ(カトリック)
近親者、親しい方を招いて教会で追悼ミサを行います。その後は教会の別室などでお茶の会を催し、故人を追悼します。ご返礼品をお届けする場合は、この日以降に行うのが通例です。
1カ月後の召天記念日(プロテスタント)
召天記念日には記念式を行います。ご返礼品をお届けする場合は、この日以降に行うのが通例です。
お悔み・お返しを贈る
- ※記載されている内容は、地域・時代・慣習・商品によって異なる場合があります。
- ※相場の金額は、三越伊勢丹の店頭にて、数多くのご相談を受けてアドバイスしてきた金額です。ただしあくまでも目安です。
お付き合いの度合いや、地域によっても変わってきます。判断に迷ったときは、少し多めの金額にするとよいでしょう。
逆に、年齢などにより金額が少なくなる場合もあります。 - ※かけ紙の表書きは代表的なものを記載しています。