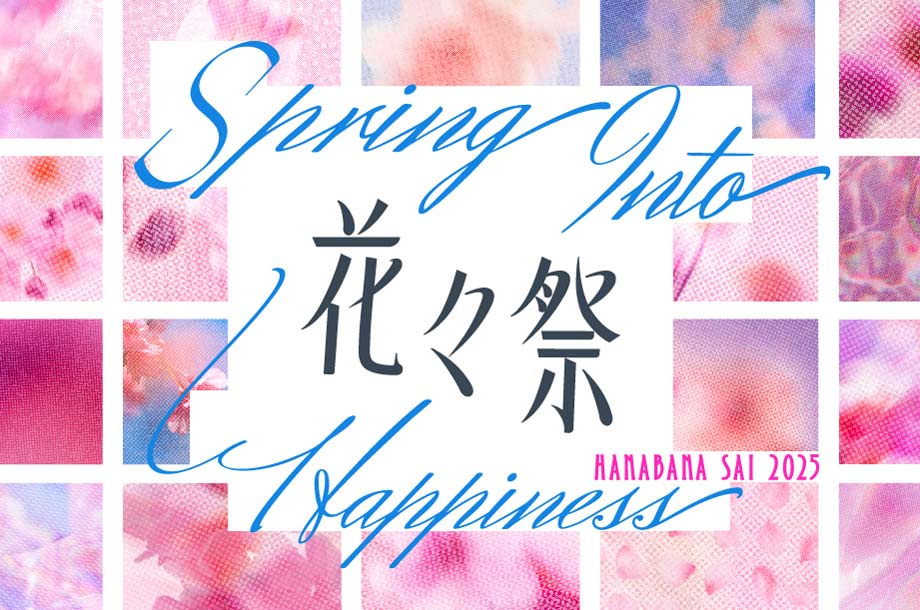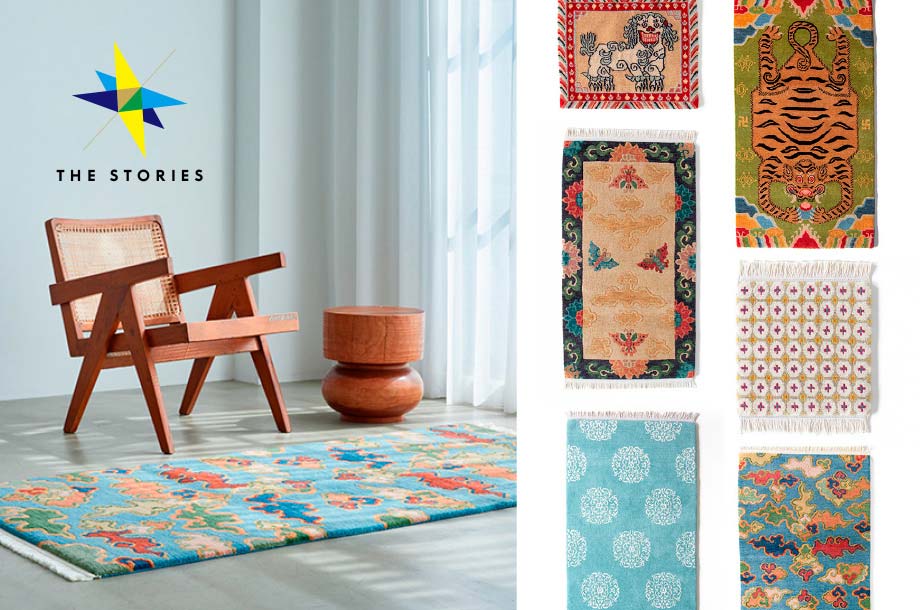新宿0丁目商店街
ICHIDA‘S LAST COLUMN「時間の旅」

2年前に始めたこの連載も、今回が最終回になりました。最後のテーマは「時間の旅」です。
取材に訪れたのは、「時間」にちなんで、神奈川県藤沢市のアンティークショップ「ジョグラール」。住宅地の中に、ぽつんと佇むお店のドアを開けると、あの人の手からこの人の手へと、受け継がれてきた品々がひっそりと並んでいます。フランスのヴィンテージを中心に、繊細でかわいらしいものから、ちょっと怖くてグロテスクなものがミックスされているのが特徴。「ジョグラール」とは、中世フランスの「旅芸人」のことなのだとか。各地を転々と遍歴しながら生活をしていた彼らは、他国の文化を継承する担い手としての役割を持っていたそう。「昔の職人が思いを込めて作り、代々大切に受け継がれ、長い時を重ねたからこその魅力を持つ品物を集めました」と、オーナーの深澤 哲さんが教えてくれました。

この日は、深澤さんの仲間でもあるアンティークディーラーの皆さんも集結。そして!
今回はスペシャルゲストが来てくださいました。<ハウス オブ ロータス>のクリエーティブディレクター、桐島 かれんさんです。古いものが好きで、今住んでいらっしゃる葉山のご自宅も、なんと築100年。まずは、みんなで古いものの魅力についておしゃべりをはじめました。

かれんさんのアンティーク好きはどこからはじまったのでしょう?
「小学校6年生から中学校1年生ぐらいまで、ニューヨーク郊外のロングアイランド、イーストハンプトンで暮らしていたんです。母(作家の桐島 洋子さん)は、途中で日本に帰ってしまって、子供たちだけが残ったのですが、そのときお世話になったのが、妹(桐島 ノエルさん)の担任の先生でした。その先生のお宅に毎週末あずけられていて、そこにナーナと私がよんでいたおばあさまがいらしたんです。ナーナは、週末にアンティークショップを営んでいたんです。だから、普通の生活の中に、当たり前のように古いものが使われていました。ベッドカバーが古い布地のキルティングだったり、ずっと昔のティディベアが並んでいたり。私は、ナーナから古いレースをたくさんもらって遊んでいました。全部今でも大切に持っているんですよ」。
かれんさんが、東京 麻布の古い洋館で<ハウス オブ ロータス>を始めたのは、今から20年以上前のこと。私もよくおじゃましていました。当時は珍しかったタイやベトナムの可愛らしい雑貨が並び、かわいいんだけれど大人っぽい、そんな世界に夢中になったなあ。
「日本人って、どうしても西洋的なものに憧れがあるけれど、アジアにもアフリカにも南米にも美しいものがたくさんあることを伝えたかったんです。アジア雑貨というと、バイヤーは男性が多いんです。だから私はファッションバッグやサンダルなど、女性の視点で選んだアジアの雑貨を紹介したいと思っていましたね」。
今<ハウス オブ ロータス>は、洋服が中心となり、クリエーティブディレクターであるかれんさんがシーズンテーマやインスピレーションを発信し、コレクション制作がスタートされています。
毎シーズンのコレクションテーマは、旅やアート、昔の記憶など。その時の気分から、この春夏は「南仏へのヴァカンス」がテーマに。


「サントロペやニース、プロヴァンスなど、コートダジュールでのヴァカンスを思い描きながらディレクションしました。ちょっと昔の、たとえばジャン・リュック・ゴダールや、エリック・ロメールの映画の世界のイメージなんです。南仏は、小さなかわいい街がたくさんありますよね。マティスの小さな教会があったり、ピカソが愛したアヴィニオンとかね。アーティスト縛りで巡っても楽しいのかも。あとはラベンダーやひまわり畑など自然が本当に素晴らしい!そんなアーティストたちに愛された心地良さを感じてもらえたら嬉しいですね」。
この日、かれんさんが着いていらしたワンピースは、トリコロールカラーや、ちょっとレトロな花柄のもの。私も、シフリー刺繍を施したワンピースを着せていただきました。



ふだんの暮らしの中では、ヨーロッパからアジアまで、国籍にこだわらず多くの古いものを使っていらっしゃるそう。
「皆さんは、どんな古いものが好きなのか、聞きたいわ」とかれんさん。

「コヴィン」の宇治橋 帆織さんは、ヴィンテージの雑貨やアクセサリーなどの小物を中心に、現地で宝探しのように、一つひとつ丁寧に集めている方。彼女の集める“小さいものクラブ”には熱烈なファンが多く、思いの詰まったセレクトとキュートな小さなものたちは
いつも物語の一部を切り抜いたように展示されています。


「ブラウンアンティークス」の山田 和博さんは、実はもと家具のデザイナー。
たくさんのディーラーの方々をまとめて、一つの世界を作り上げる0丁目商店街に欠かせない方のお一人だそう。


「アンティークに関わってからは、自分が作るという欲求よりも、よい素材を使って、ものづくりに時間をかけていた時代のものを、紹介したいという気持ちになったんです。古いもののよさって、僕らが『時間』を追いかけているというところなんじゃないかと思います」
「新宿0丁目商店街」の組合長の原田 陽子さんが、10年前に初めて伊勢丹新宿店で、ヴィンテージのあれこれを集めた企画展を開催したのは、山田さんとの出会いがきっかけだったそうです。
「10年以上ずっと一緒にお仕事をさせていただいています。集まるメンバーは毎回ほとんど変わりません。でも、皆さんが作ってくださる世界は、一度たりとも同じであったことはなく、常に進化し続けて、その都度集めてきてくださるものが、本当にお客さまの感動を呼んでいるんです」と原田さん。

「古い時代のものの中には、今はもう作れないものがたくさんあります。だから、そこには人間の技のピークが見える・・・。今は、こんなに進んだ世の中なのに、実は手仕事の面ではどんどん退化してしまっていますよね。だから、本当にいいものを見るためには、過去に遡らないといけない。今は昔より豊かになっているはずなのに、豊かじゃなくなっているところもあるかも」とかれんさん。
「その通りだと思います。たとえば金属のカトラリーだと、大量生産だとどんどん薄くなっていくけれど、古いものだとしっかり手で作られているから重い。ディーラーにとって、仕入れられるのは1点ものが多いので、宝探しみたいな快感があるかもしれませんね」と深澤さん。


好きなものが同じだと、今日あったばかりなのに、話がどんどん弾みます。
昨年、かれんさんはお母さまの洋子さん、妹のノエルさん、弟のローランドさんとの共著として「ペガサスの記憶」という本を上梓されました。フリージャーナリストとしてマスメディアで活躍するかたわら、未婚のまま3人の子供を産み、育て上げ、「女性の自立と成熟」の代名詞として絶大なる人気を集めた洋子さん。破天荒で波瀾万丈のこの自伝を連載されている途中、2014年にアルツハイマー型認知症と診断され、執筆を続けることができなくなりました。そこで、かれんさん、ノエルさん、ローランドさんが、バトンタッチをし、手分けをして第2章を書き上げ、壮大な物語が完成したのでした。
今回、かれんさんに「人生の時間」についてもお話を伺ってみました。

「アルツハイマーって、本人は病気だってわからないんですよね。だからずっと仕事もバリバリとこなしていました。でも、まさにこの連載を書いている途中に、あるところでパタッと筆が止まってしまったんです。このまま終わらせるのはもったいないと思い、私たちで、その後の話を紡いでいきました。『ペガサスの記憶』は、連載のためのタイトルでした。『ペガサス』はローマ神話の不死身の象徴です。そして、『記憶』という言葉を使っているのが、なんだか不思議ですよね。母は、記憶をなくしながら、自分の過去を書いていたことになります。まあ、今もいたって元気なんですけれどね。アメリカでは、アルツハイマー病は、「神様からの贈り物」って言われているんです。癌などの病気なら死の恐怖と向き合わなくてはいけないけれど、アルツハイマーでは、死という概念、恐怖すらもいずれわからなくなるから。今、母は昔のことはよく覚えているので、母娘で、当時の話をしているんですよ」。
仕事のこと、恋愛や出産のことなどをノンフィクションで綴ってきた洋子さん。かれんさんは、そんな破天荒な母のことが恥ずかしかった時期もあったそう。


「いつも民族衣装を着て、街中を歩くような人だったので『友達に見られたらどうしよう!』って、『この人は私の母親じゃありません』みたいな顔をしていました。でも、気づけば、私もアオザイを着たりと、そういう女になっちゃった!(笑)反抗しても、結局は影響を受けていたんですね」。
時が経てば、家族の在り方は少しずつ変わってきます。人は必ず老い、できないことが増えてきます。実は、かれんさんと私は同じ1964年生まれの同じ歳です。人生後半の時の流れについて、どう考えていらっしゃるのでしょうか?
「人生を山登りにたとえると、登っているときには、その先が見えないんですよね。若い頃はその先に、下り坂が続いているなんて、思ってもいませんでした。でも、頂上に立ったとき、突然そこからは人生の最後が見渡せるようになります。つまり死が見える・・・。それがたぶん50歳ぐらい。「おおそうか、私ももう残り半分か」っていうことを実感しました。母がいつも言っていたのは、『人生っていうのは、木の年輪みたいなもの』ということでした。年輪はバームクーヘンのように重なっていって、雨風にさらされて、外側はガビガビに固くなっていきます。でも、その中心は、柔らかくてきれいなままなんです。母が言いたかったのは、自由な人間は、たとえ80歳になったとしても、瞬時に若かりし頃の自分の気持ちに戻ることができる、ってことですね。年輪の中心にある自分を覚えているというか・・・。たとえば、初めてキスをしたときのドキドキした気持ちとか・・・。そういうところへ時間の行き来ができれば、ずっと生き生きとしていられるはず。年輪の外側のことばかり気にするのではなく、内側へ戻ってくればいい。私も娘に素敵なボーイフレンドができたのを見ると、瞬時に私もその頃の気持ちに戻れますし、映画を見たって、キュンと切なくなったりします。そうやって、時代を行き来しながら成長していくほうが、人生が楽しくなると思いますね。20歳の頃の自分と比べて、何が変わったのかなと考えてみても、たぶんコアな部分はなにも変わっていないんですよね。中身は少年少女のまま、何か好きなことがあって、それを忘れなければいい。少年少女時代の自分を大切にすればいい。何か好きなことがあって、夢中になれるものがあって、没頭すると時間も忘れてしまうみたいなのが1番の贅沢だと思います」。
かれんさんが、サディスティックミカバンドのヴォーカルとしてデビューしたのは、25歳の時でした。やがて写真家の上田 義彦さんと結婚。3女1男の母となります。息子さんはもう大学生。時は刻々と流れ、いろんなことが変化するけれど、母に受け継いだ美しい言葉遣いや、自分の好きな道を行く勇気や、上質なものを見抜く目は、ずっと変わることがありません。さらさらと流れる時によって、消化されるものはあるけれど、確かに残るものもある・・・。お母さまから受け継いだ宝物を磨き続けながら、自分らしく佇むかれんさんの姿がそう教えてくれているよう。

「新宿0丁目商店街」は、これからも新たな扉を開ける予定です。その向こうにどんな世界が広がっているかは乞うご期待。人をドキドキさせるものを見つけて、組み合わせ、想いをパンパンに詰め込んでお客さまをお迎えする。その心は、ずっと変わることがありません。

文・一田 憲子さん
ライター・編集者として女性誌、単行本の執筆などを手がける。2006年、企画から編集、執筆までを手がける「暮らしのおへそ」を2011年「大人になったら、着たい服」を(共に主婦と生活社)立ち上げる。著書に「日常は5ミリずつの成長でできている」(大和書房)「暮らしを変える 書く力」(KADOKAWA)「もっと早く言ってよ。」(扶桑社)新著「人生後半、上手にくだる」(小学館)「明るい方へ舵を切る練習」(大和書房)自身のサイト「外の音、内の音」を主宰。http://ichidanoriko.com
写真・近藤 沙菜さん
大学卒業後、スタジオ勤務を経て枦木 功氏に師事。2018年独立後、雑誌・カタログ・書籍を中心に活動中。
スペシャルゲスト
<ハウス オブ ロータス>クリエーティブディレクター桐島 かれんさん
ヴィンテージディーラー
<ブラウン アンティークス> 山田 和博さん
<コヴィン> 宇治橋 帆織さん
<ジョグラール> 深澤 哲さん(撮影ショップ)

2年間、たくさんの時間の変化の中、わがままを言って始めた「ICHIDA‘S COLUMN」。
「百貨店」の内側にいる、普段もしかしたら出会うことのない仲間たちを取材していただいたり、いろいろな人たちのこだわりを見つけにおでかけしたり、一つひとつのコラムを読み返しても忘れられない素敵な思い出と0丁目の財産となりました。
一田 憲子さん、カメラマン近藤 沙菜さん本当にありがとうございました。
またすぐ、妄想の旅を企画してお二人をお誘いできるように、これからも0丁目商店街ののれんをかけ続けますね。
新宿0丁目商店街組合長・原田 陽子