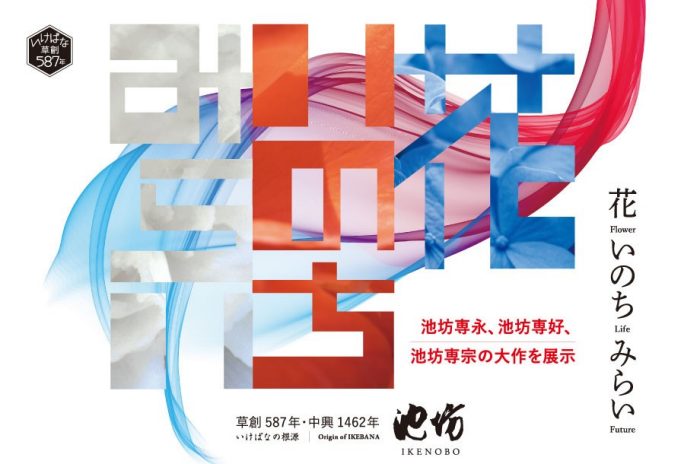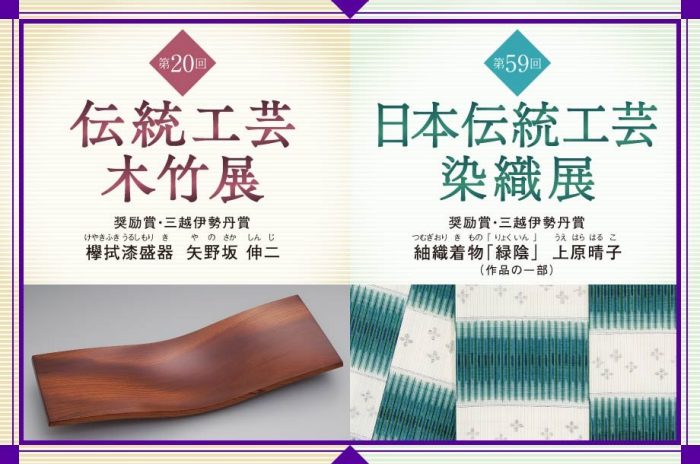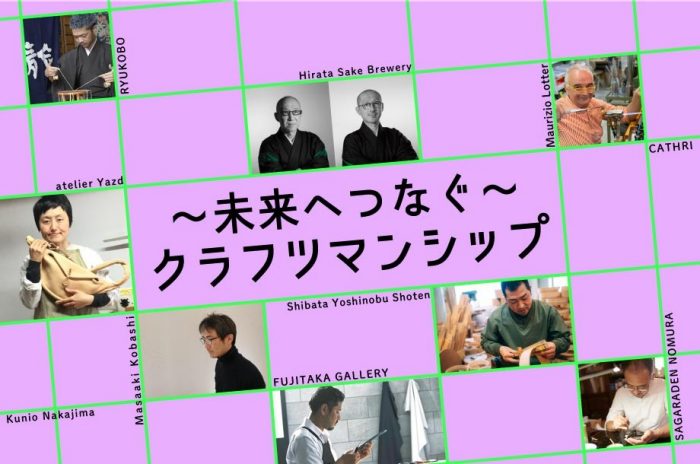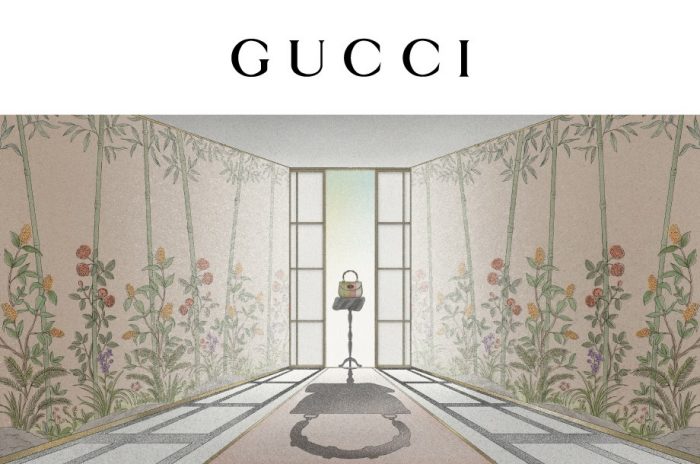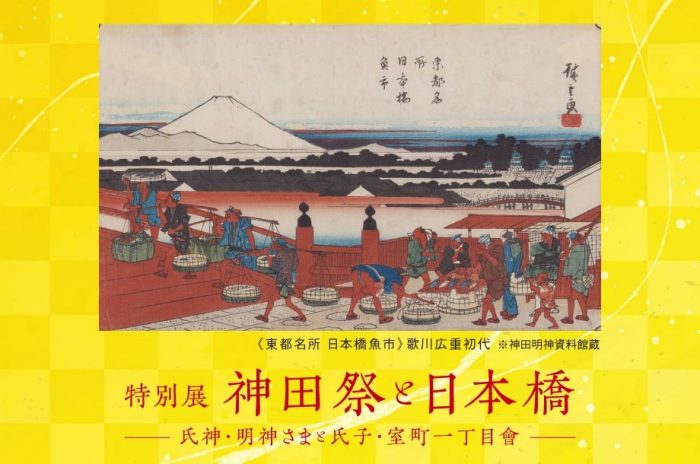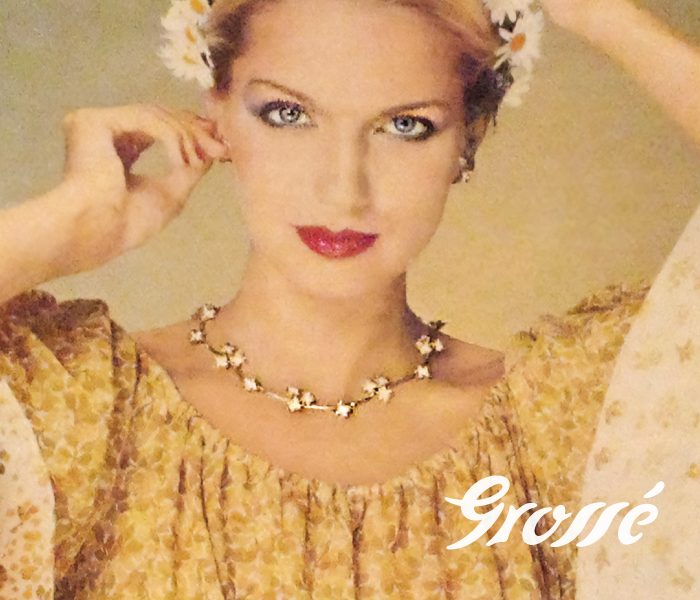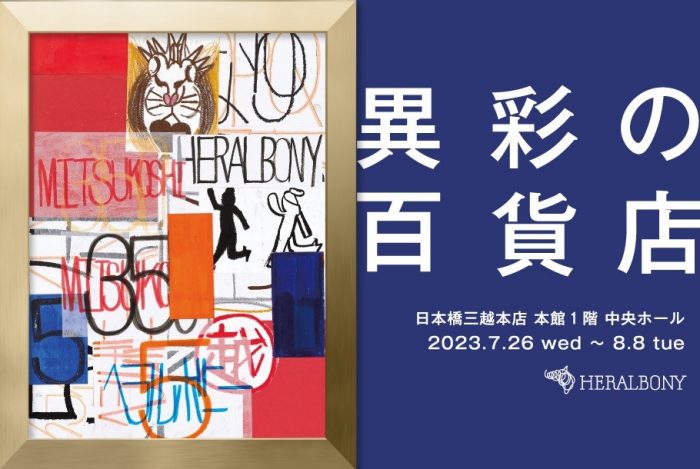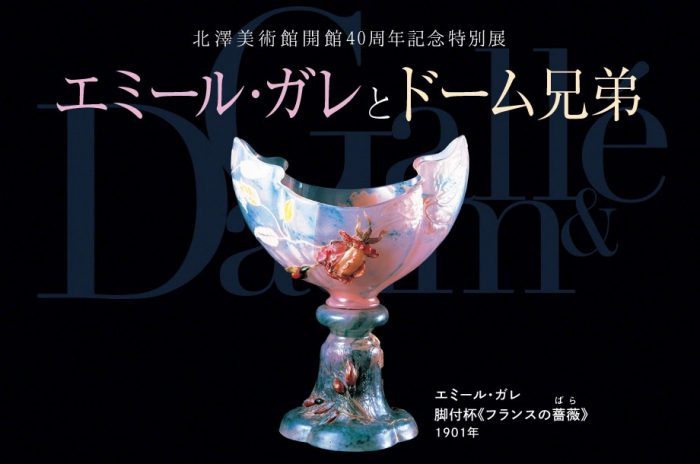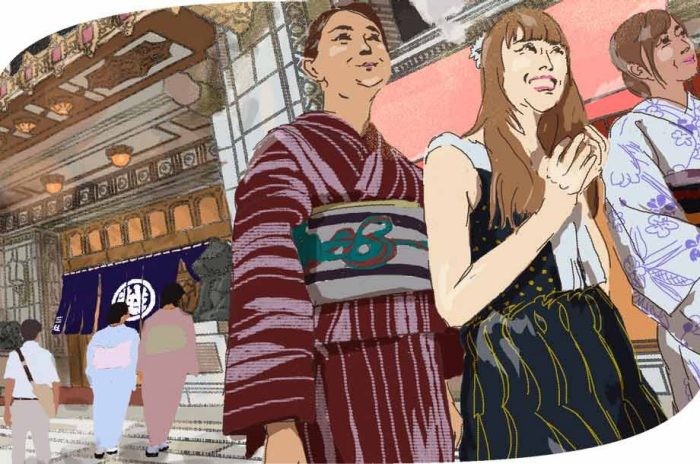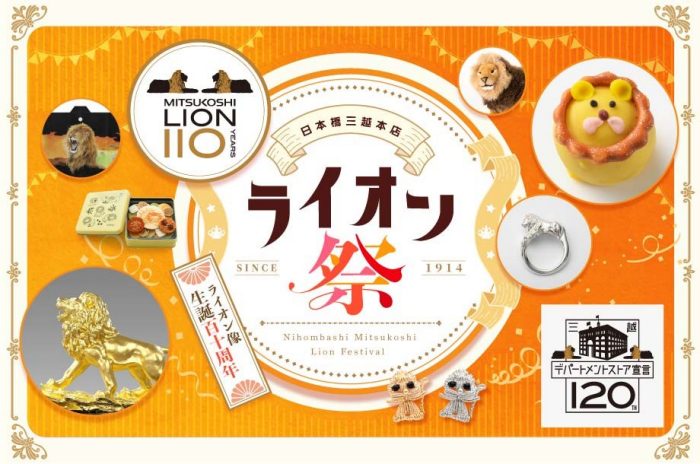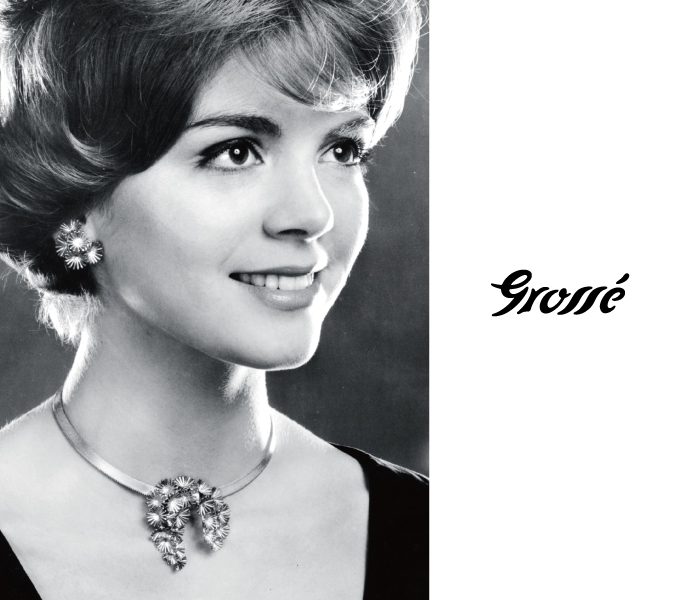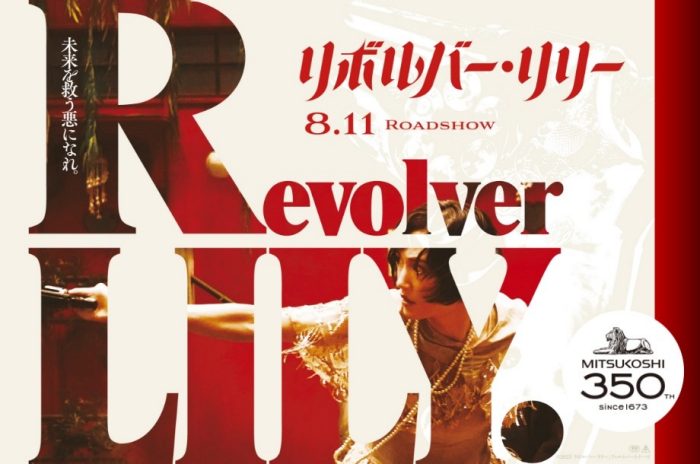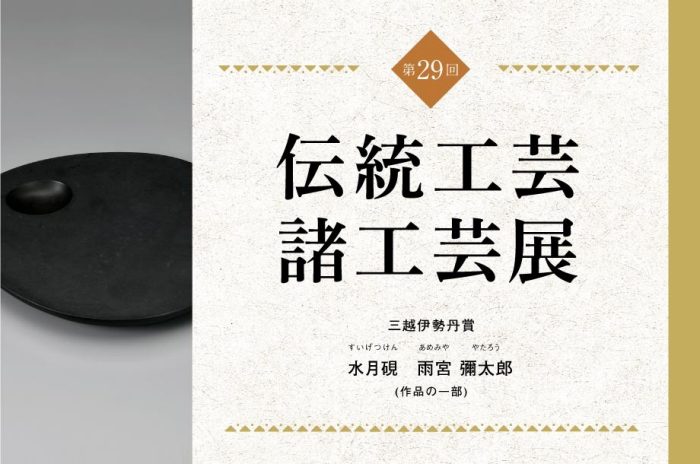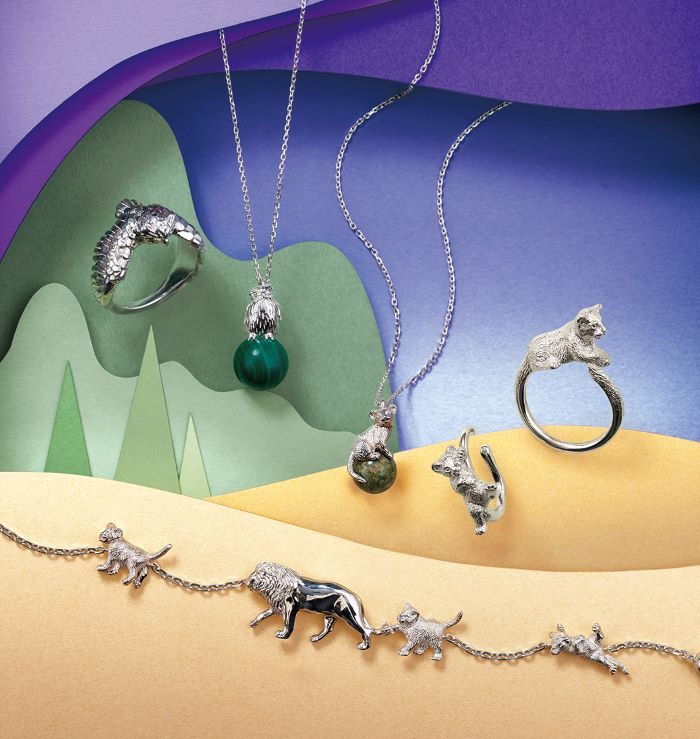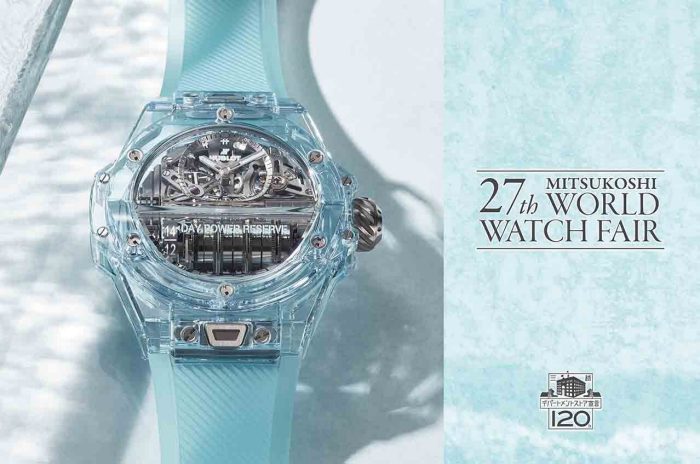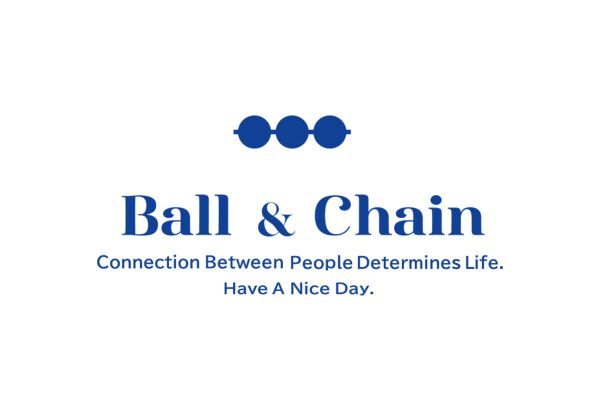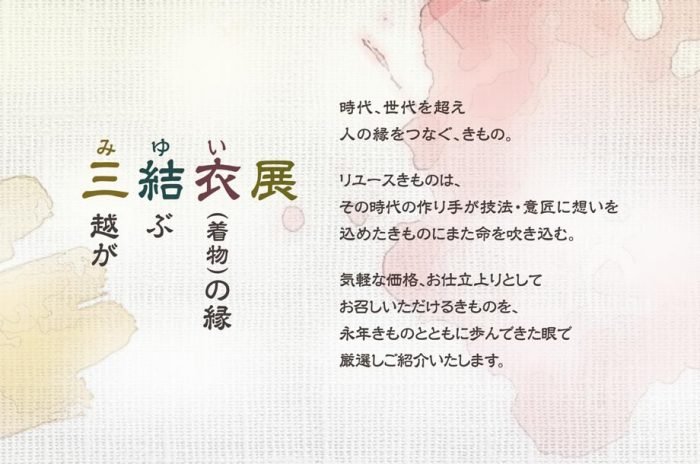<Grosse/グロッセ>Summer Resort Collection
6月18日(水) ~ 6月24日(火)
SALE メンズサマーバザール
6月11日(水) ~ 6月16日(月)
※最終日は午後6時終了
第65回 東日本伝統工芸展
5月14日(水) ~ 5月19日(月)
※最終日午後6時終了
スプリングフェスタ
3月5日(水) ~ 4月1日(火)
再興第110回院展記念展 同人たちの出世作といま ー無窮をめざしてー
2月19日(水) ~ 3月3日(月)
※最終日は午後6時終了 ※ご入場は各日終了30分前まで
神戸セレクトマーケット
2月15日(土) ~ 2月17日(月)
※最終日午後6時終了
スイーツコレクション 2025
1月29日(水) ~ 2月14日(金)
※最終日は午後6時終了
北海道展 PART2
1月15日(水) ~ 1月20日(月)
※最終日は午後6時終了
<GEORG JENSEN/ジョージ ジェンセン> CELESTIAL CHRISTMAS
11月27日(水) ~ 12月3日(火)
第14回 東京まん真ん中 味と匠の 大中央区展
10月23日(水) ~ 10月28日(月)
※最終日は午後6時終了
第71回 日本伝統工芸展
9月11日(水) ~ 9月23日(月·振替休日)
※最終日午後5時終了
英国展 2024 PART2
9月4日(水) ~ 9月9日(月)
※最終日午後6時終了
MITSUKOSHI Art 昭和・平成・令和 時代を切り拓く絵師たち
8月21日(水) ~ 8月25日(日)
※最終日は午後6時終了
Disney THE MARKET in 日本橋三越本店
8月7日(水) ~ 8月19日(月)
※最終日は午後6時終了
2024 Summer MITSUKOSHI Art Selection
7月10日(水) ~ 7月22日(月)
※最終日は午後6時終了
2024 MITSUKOSHI ART selection 【同時開催】還暦記念ジミー大西原画展
1月24日(水) ~ 1月29日(月)
長坂真護展 Still A BLACK STAR truth of capital
8月23日(水) ~ 8月28日(月)
<プレ展示> 2023年8月16日(水)〜8月22日(火)※最終日午後6時終了
夏のあんこ博覧会
6月25日(水) ~ 6月30日(月)
※最終日は午後6時終了
SALE アクセサリー&ジュエリーバザール [同時開催]黄金フェア
6月4日(水) ~ 6月9日(月)
※最終日午後6時終了
第69回 とっておきの山形展
5月28日(水) ~ 6月2日(月)
※最終日午後6時終了 ※イートインラストオーダー:各日終了30分前
いけばなの根源 池坊展
5月21日(水) ~ 5月26日(月)
※最終日午後6時30分終了
2025 MITSUKOSHI Art Week
5月14日(水) ~ 5月19日(月)
※最終日は午後6時終了
第59回 日本伝統工芸染織展 第20回 伝統工芸木竹展
5月8日(木) ~ 5月12日(月)
※最終日は午後6時終了
第68回 旬味まるごと 三重展
4月9日(水) ~ 4月14日(月)
※最終日午後6時終了
第80回 春の院展
3月26日(水) ~ 4月7日(月)
※ご入場は各日終了30分前まで ※最終日午後5時終了
旭山動物園"もっと夢"基金×<ヴァンドームブティック> ~新年に願いを込めて~
1月8日(水) ~ 1月14日(火)
ペルシャ絨毯フェスタ 同時開催:ひとりでくつろぐ豊かな日常
12月3日(火) ~ 12月9日(月)
※最終日は午後6時終了
大黄金展
11月27日(水) ~ 12月1日(日)
※最終日は午後6時終了。
Happy Art Movement ロメロ ブリット展
10月30日(水) ~ 11月4日(月·振替休日)
※最終日は午後6時終了
第75回 京名物 洛趣展
10月9日(水) ~ 10月14日(月·祝)
※最終日は午後6時終了。
フランス展 2024 PART2
10月2日(水) ~ 10月7日(月)
※10月1日(火)は会場準備のため終日閉場いたします。
英国フェア 2024
8月28日(水) ~ 9月10日(火)
~出会い、笑顔、旅のまにまに~ さだまさし展
7月10日(水) ~ 7月22日(月)
最終日 午後6時終了
SALE レディースファッションバザール
5月8日(水) ~ 5月13日(月)
※最終日は午後6時終了
手塚雄二展
2月14日(水) ~ 3月5日(火)
※最終日は午後6時終了
<GEORG JENSEN/ジョージ ジェンセン> LEGACY 2023
7月5日(水) ~ 7月18日(火)
第19回 伝統工芸木竹展
6月21日(水) ~ 6月26日(月)
※最終日は午後6時終了
~未来へつなぐ~ クラフツマンシップ
8月17日(水) ~ 8月30日(火)
GUCCI BAMBOO ROOM
11月17日(水) ~ 11月30日(火)
三越のゆかた2025
3月26日(水) ~ 8月26日(火)
第32回 伝統工芸人形展 第30回 伝統工芸諸工芸展
6月18日(水) ~ 6月23日(月)
※最終日は午後6時終了
レディース フィットネス& スイムウェア フェスタ
5月28日(水) ~ 6月2日(月)
※最終日午後6時終了
特別展 神田祭と日本橋 -氏神・明神さまと氏子・室町一丁目會-
5月7日(水) ~ 5月19日(月)
ワコールスペシャルバザール
5月8日(木) ~ 5月12日(月)
※5月8日(木)はエムアイカード プラス・エムアイカード ベーシック会員さま特別ご招待日※最終日午後6時終了
真珠展
4月9日(水) ~ 4月14日(月)
※最終日午後6時終了
第79回 全国銘菓展
3月19日(水) ~ 3月24日(月)
※最終日は午後6時終了
ココロ躍る文具の祭典 三越文具祭り 2025
2月16日(日) ~ 2月24日(月·振替休日)
三越アンティーク&ビンテージ −時を巡るマーケット
1月22日(水) ~ 1月27日(月)
※最終日は午後6時終了
<グロッセ>2025 Spring Flower Collection
1月15日(水) ~ 1月21日(火)
大歳の市
12月26日(木) ~ 12月31日(火)
※12月31日(火)は本館・新館 地下階、本館1階 中央ホール 大歳の市特設会場は 午前9時30分~午後5時閉店。
2024 日本橋三越本店のクリスマス
11月6日(水) ~ 12月25日(水)
みつイモ!—三越サツマイモ祭り—
11月13日(水) ~ 11月18日(月)
※最終日は午後6時終了
<MARNI MARKET/マルニ マーケット>
9月4日(水) ~ 9月10日(火)
三越の七五三大祭典
8月21日(水) ~ 8月25日(日)
※最終日午後6時終了
Good Life in Summer~夏を快適に過ごすアイテム~
7月24日(水) ~ 8月6日(火)
おかげさまで、三越創業350周年
3月6日(水) ~ 3月19日(火)
<Grossé> Grossé Three Generations
9月6日(水) ~ 9月19日(火)
<HERALBONY> POPUP STORE
7月26日(水) ~ 8月8日(火)
三越と松竹衣裳所蔵 歌舞伎衣裳展
7月5日(水) ~ 7月17日(月·祝)
※最終日は午後6時終了
エミール・ガレとドーム兄弟
2月16日(木) ~ 2月27日(月)
※最終日は午後6時終了 ※ご入場は、各日終了30分前まで
高橋真琴展
7月20日(水) ~ 7月25日(月)
最終日は午後6時終了
イラストレーター45周年記念 鈴木英人の世界展~Welcome to your dream journey~ 【同時開催】手塚治虫 版画展~TVアニメ『ジャングル大帝』放送60周年~/ちばてつや 版画展
3月19日(水) ~ 3月24日(月)
※最終日午後6時終了
大九州展
3月5日(水) ~ 3月10日(月)
※最終日は午後6時終了
日本橋三越の迎春
11月27日(水) ~ 12月31日(火)
三越の父の日
5月29日(水) ~ 6月16日(日)
日本橋三越本店 ライオン祭
4月24日(水) ~ 5月14日(火)
春のメガネフェア
2月16日(金) ~ 2月20日(火)
※最終日は午後6時終了
<Grosse/グロッセ> 2024 Spring Collection ~Blooming
1月31日(水) ~ 2月6日(火)
番組放送30周年記念 ぶらり途中下車の旅 沿線おいしいもの&アート巡り
7月19日(水) ~ 7月24日(月)
※最終日は午後6時終了
映画『リボルバー・リリー』衣裳&写真展
7月12日(水) ~ 7月18日(火)
第29回 伝統工芸諸工芸展
6月28日(水) ~ 7月3日(月)
※最終日は午後6時終了
新潟ものづくり展
2月16日(木) ~ 2月20日(月)
※最終日は午後6時終了
メンズスペシャルバザール
6月1日(水) ~ 6月6日(月)
日比野克彦展「Xデパートメント 2020」
3月18日(水) ~ 3月30日(月)
※最終日は午後5時閉場
キャプテン翼原画展 ~FINAL そして未来へ~
7月24日(水) ~ 8月5日(月)
最終日 午後6時終了
マイセン展
11月22日(水) ~ 11月27日(月)
※最終日は午後6時終了
三越創業350周年・リヤドロ創業70周年 リヤドロ展
8月23日(水) ~ 8月28日(月)
※最終日は午後6時終了
旭山動物園“もっと夢”基金×ヴァンドームブティック応援企画 期間限定POP UP SHOP
7月19日(水) ~ 7月25日(火)
三越 食賓祭
11月16日(水) ~ 11月21日(月)
※最終日は午後6時終了
夏の手土産
7月27日(水) ~ 8月16日(火)
SLEEPY LAND〜眠るのが楽しみになるモノ・コトが集結 快眠をご提案〜
3月12日(水) ~ 3月17日(月)
※最終日は午後6時終了
日本の職人 匠の技展
12月27日(金) ~ 1月6日(月)
※最終日午後6時終了※12月31日(火)は午前10時〜午後5時。 本館・新館 地下階、本館1階 中央ホール 大歳の市特設会場は午前9時30分開店。 ※新年は1月2日(木)午前10時から初売出し。午後6時まで営業。 ※1月1日(水・祝)は店舗休業日とさせていただきます。
SALE メンズ&レディースウィンターファッションバザール
12月18日(水) ~ 12月25日(水)
最終日は午後6時終了
Good Life in Winter ~冬じたくのすすめ~
11月6日(水) ~ 11月26日(火)
第27回 三越ワールドウォッチフェア~時をつなぐ、時を楽しむ~
8月14日(水) ~ 8月27日(火)
#ちああっぷ 〜⼥性を想い、エールを送るウィーク〜
3月6日(水) ~ 3月19日(火)
三越のお中元 2025 夏の贈り物 お中元ギフトセンター
6月4日(水) ~ 7月21日(月·祝)
※最終日は午後6時30分終了
三結衣展(みゆいてん)~リユースきものの魅力~
3月12日(水) ~ 3月17日(月)
日本橋三越 新春祭 2025
1月2日(木) ~ 1月4日(土)
第65回 2024年 報道写真展
12月11日(水) ~ 12月22日(日)
最終日 午後6時終了
ペルシャ絨毯バザール 同時開催:椅子のある暮らし
11月1日(水) ~ 11月6日(月)
※最終日は午後6時終了。
三越の振袖大祭典
3月12日(水) ~ 3月17日(月)
<Ball&Chain/ボール&チェーン> POP UP SHOP
1月15日(水) ~ 1月21日(火)
三越のお歳暮 2024 冬の贈り物 お歳暮ギフトセンター
10月30日(水) ~ 12月22日(日)
※最終日は午後6時終了
三結衣展
3月13日(水) ~ 3月18日(月)
※最終日は午後6時終了
箱根駅伝100回記念 報道写真で振り返る箱根駅伝展
12月27日(水) ~ 1月9日(火)
最終日 午後6時終了



















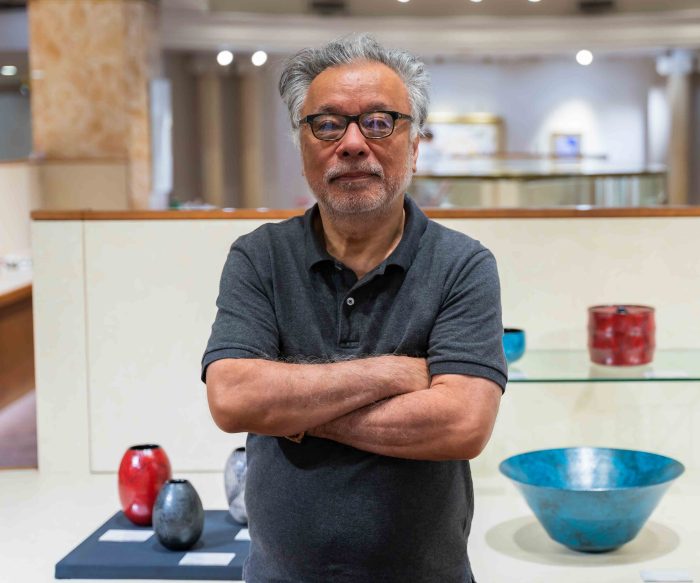
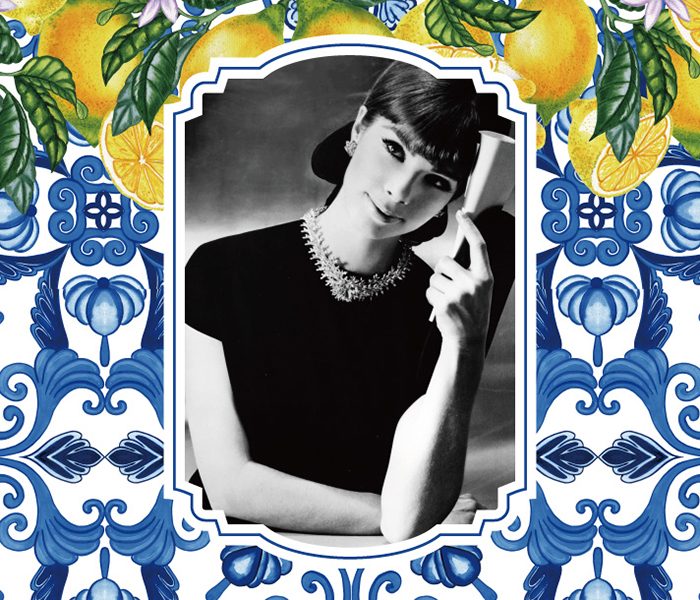



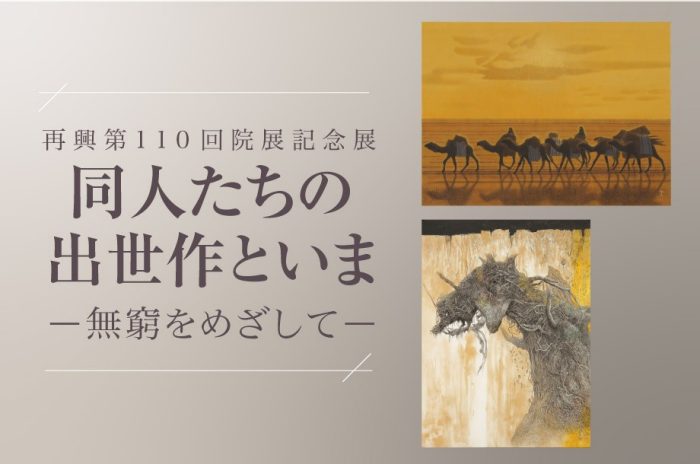





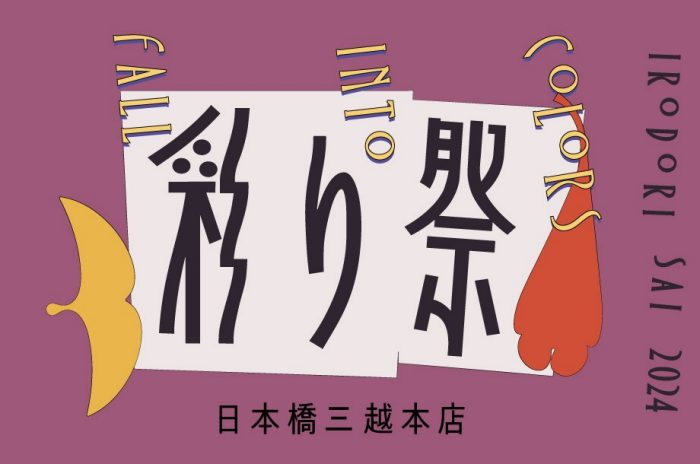






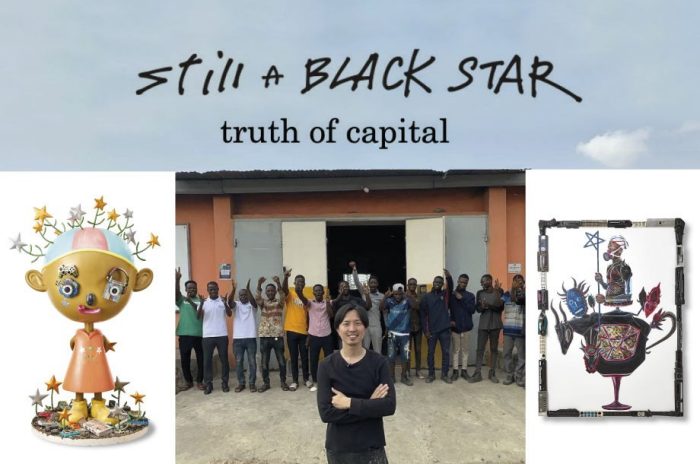

![SALE アクセサリー&ジュエリーバザール [同時開催]黄金フェア](/content/dam/isetan_mitsukoshi/site/nihombashi/top/bnr/jewerly_50.jpg.transform/thumbnail/img.jpg)